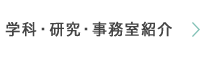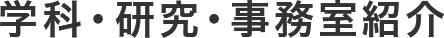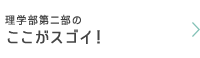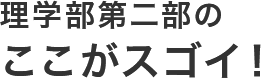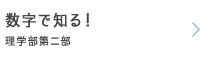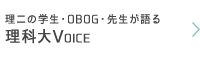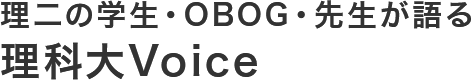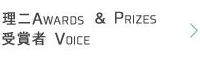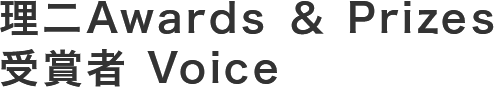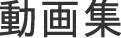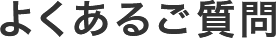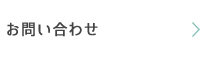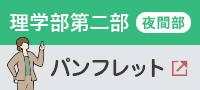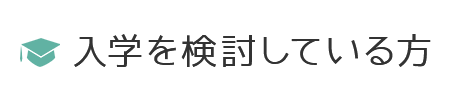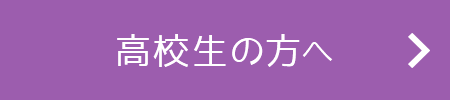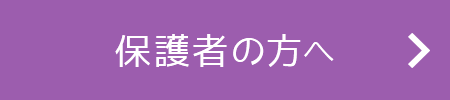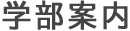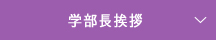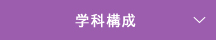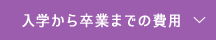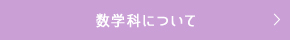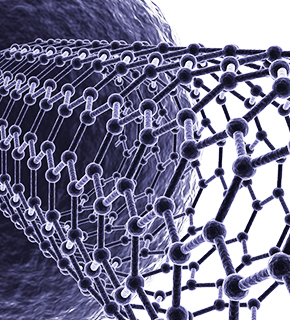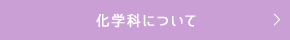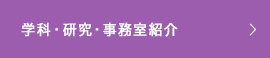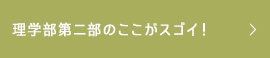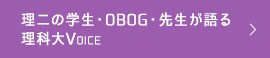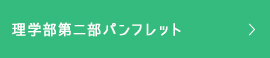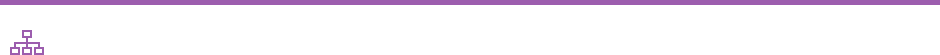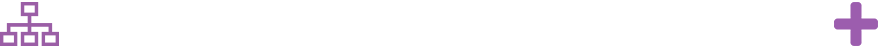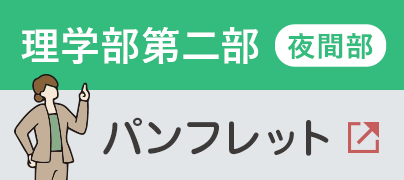学部長挨拶

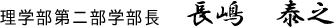
理学部第二部では、建学以来の精神である「理学の普及」と、真に実力をつけた学生のみを卒業させるという「実力主義」の教育方針を基本理念として、大学教育を行っています。本学の歴史は、1881年に「東京物理学講習所」が創設され、社会人を対象とした夜間教育を行うことからスタートしました。それは理学部第二部の歴史そのもので、今日までその精神は引き継がれています。現在では、若い学生や企業人、会社経営者や芸術家、医師など、いろいろな人たちが共に学び、卒業後は社会で活躍できる科学者となることを目指して、高度な教育を受けています。このため、若い学生は社会人学生から様々な知識をもらい、社会人学生は若い学生からエネルギーをもらう、という他では味わえない環境が出来上がっています。
理学部の第二部のカリキュラムが第一部と異なるのは、講義の時間帯が夜間であることだけです。第一部と同様に4年制の大学で、学ぶ内容も理学部第一部とほぼ同じです。
理学部第二部の学生の構成は、おおよそですが、社会人が2割で普通の学生が8割となっています。昼間部の学部に比べて社会人の比率が高いので、授業の熱心さが違います。企業での開発現場から通ってくる学生もいますので、授業中の質問は鋭く高度なものであったりします。このようなことは昼間部の授業ではあまり見られないもので、学生にとっても非常に刺激的なものとなります。さらに本当に中学や高校の教員になりたい、という人たちもたくさんいて、教員免許を取得するためのノウハウや、採用試験に関する情報交換も活発です。このようないろいろな人たちが集っていることが理学部第二部のパワーの源です。
教育は、おもに研究の最先端でも活躍する理学部第二部専任の教員によって行われています。理学部第二部の教員は、夜間学部における教育に関する経験が豊富です。その一方で、学生の皆さんは、昼間部で開講されている選択科目や教職科目の一部も、受講可能となっています。
卒業後は、教員、公務員、会社員など様々な選択肢の中から自らの適正にあった職に就いています。また30%程度は大学院に進学しています。進学先は東京理科大学大学院、国公立大学大学院など様々です。
受験生の皆さんや保護者の方々には、理学部第二部を今までの「夜間」のイメージではなく、「ライフスタイルに合わせて効果的な学習ができる新たな選択肢」ととらえていただきたいと考えています。
学科構成
理学部第二部は上記3学科で構成されており、全て1学年120名の定員で運営しています。
また、学科・研究・事務室紹介のページにあるように、学部には教養に所属し、教養科目教育を担当している先生方もおられます。
入学から卒業までにかかる費用(2024年度)
| 入学金 | 授業料
(1年分) |
施設設備費
(1年分) |
実験実習費 | その他 | 入学から卒業までに
かかる費用概算 (卒業研究費は含まず) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部第二部 | 数学科 | 150,000円 | 670,000円 | 160,000円 | -*1 | 46,920円*2 | 3,516,920円 |
| 物理学科 | 719,000円 | 3,712,920円 | |||||
| 化学科 | 730,000円 | 3,756,920円 | |||||
参考資料
| 入学金 | 授業料
(1年分) |
施設設備費
(1年分) |
実験実習費 | その他 | 入学から卒業までに
かかる費用概算 (卒業研究費は含まず) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学*3 | 282,000円 | 535,800円 | - | -*4 | -*4 | 2,425,200円 |
| 私立大学理科系学部*5 | 251,029円 | 1,136,074円 | 177,159円 | -*4 *6 | -*4 *6 | 5,511,961円 |
理学部第二部各学科の卒業研究費
| 数学科 | 卒業研究 | 0円 |
|---|---|---|
| 物理学科
(Aは必修、Bは選択必修) |
卒業研究(A) | 0円 |
| 卒業研究(B)・実験系 | 31,000円 | |
| 卒業研究(B)・理論系 | 8,000円 | |
| 化学科
(右のA、B、Cから1つを選択) |
卒業研究(A) | 16,000円 |
| 卒業研究(B) | 51,000円 | |
| 卒業研究(C) | 0円 |
- *1東京理科大学では、実験実習費は授業料に含まれている
- *2その他は、父母会費(こうよう会)、学生障害共済補償費の合計額
- *3文部科学省令による標準額
- *4大学、学部によっては徴収する場合あり
- *5令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
- *6データは発表されていません
理学部第二部の各学科の入学から卒業に至るまでにかかる費用の概算です(教科書や参考書代はここには含まれていません)。学費、施設設備費は半期単位での納入が可能です。この他に他学科実験等を履修する場合、選択科目の実験実習費が必要になったり、授業料が改訂になったりすることもあります。そのため、あくまでもおおよその目安として考えてください。なお、学科によって授業料が異なっているのは、実験実習費が授業料に含まれているためです。
沿革
| 1881年 | 東京大学出身の20才から29才の若き理学士21名が、東京都麹町区飯田町の稚松小学校を借りて「東京物理学講習所」を創立。理学普及の志に燃える同志たちは、昼は仕事を持ち夜間に無給で講義を行った。
入学試験は行わず希望者を全て入学させたが、卒業に要する条件は厳しかった。「門戸は広く開けても、卒業は厳しい」という東京理科大の伝統は、創立当初から今日まで引き継がれてきたものである。東京物理学講習所の始まりが夜間教育だったことは、理学部第二部が理科大の歴史そのものであると言われる由縁である。 |
|---|---|
| 1882年 | 東京都神田区今川小路に、同志たちがポケットマネーを出し合い、自前の校舎を建築。 |
| 1883年 | 「東京物理学校」に改称。東京大学仏語物理学科を主席で卒業し、5年間のフランス留学を終えた寺尾寿が初代校長に就任。寺尾は帰国後、東京大学で天文学と数学の講師となり、翌1884年には28才で教授に昇格している。 |
| 1884年 | 今川小路校舎が台風により倒壊。以後3年間に5回校舎を転々とする。 |
| 1888年 | 神田小川町の仏文会校舎を買い取る。当初、20名の学生から始まった物理学校は、この時303名の学生を擁するまでになっていた。また、東京職工学校(現東京工業大学)の予備校となるための学科カリキュラムを作り、社会人や国公立大学入学を希望する若い人材に、広く理学を教える学校として機能。 |
| 1893年 | 日本初の物理学の教科書「普通物理学教科書」全3巻を、物理学校維持同盟16名により刊行。 |
| 1906年 | 神楽坂に新校舎建築。これまでの理数教員養成に関する高い評価から、東京物理学校は各種学校であったにもかかわらず、卒業生は文部省の中等教員検定試験を受験する資格を与えられる。当時理学教育者養成は、理学普及にとって最重要事項の一つであったが、現在も教育者の育成は、理学部第二部にとっても大きな使命として受け継がれている。 |
| 1916年 | 卒業生の小倉金之助氏が東北帝国大学で博士号の学位を取得し、物理学校卒業生初の理学博士が誕生する。 |
| 1917年 | 専門学校認可が出て、専門学校・東京物理学校となる。 |
| 1923年 | 関東大震災により、神田から銀座方面まではほぼ全壊であったが、物理学校校舎は大きな被害を免れた。 |
| 1931年 | 実力主義を唱え続けて迎えた創立50周年。理学教育機関として、揺るぎない地位を確立。 |
| 1949年 | 学制改革により「東京理科大学」となり、理学部第一部、理学部第二部からなる、日本最初の理工系単科大学が誕生。本多光太郎が初代学長となる。 |
以降、東京理科大学は、8学部33学科、11研究科31専攻を擁するまでに発展。理学部第二部は現在、東京理科大学としての設立当初より理学部第一部と密な協力体制を取りながら、理数系教員をはじめ優れた人材を数多く輩出している、日本で唯一の夜間理学部となっています。