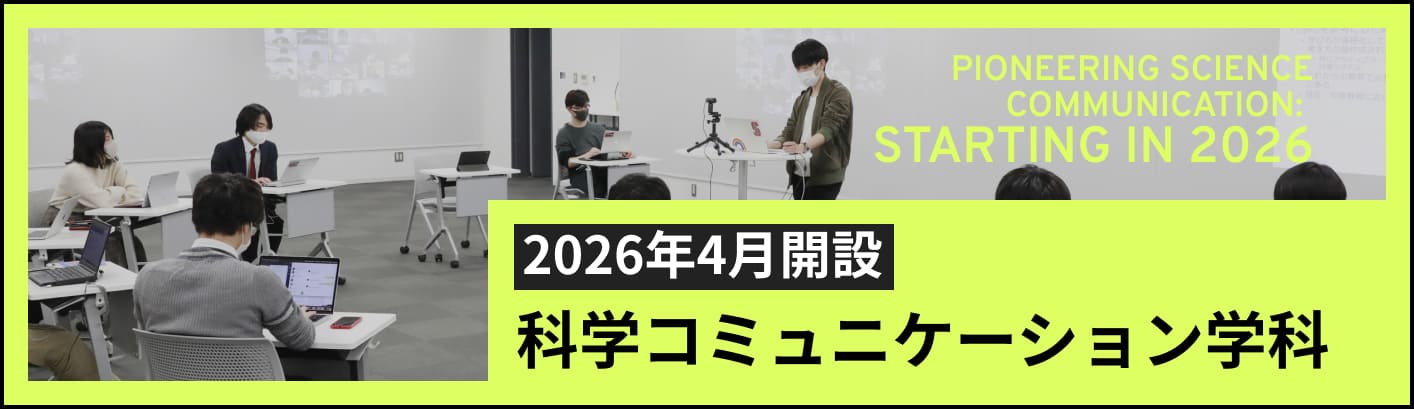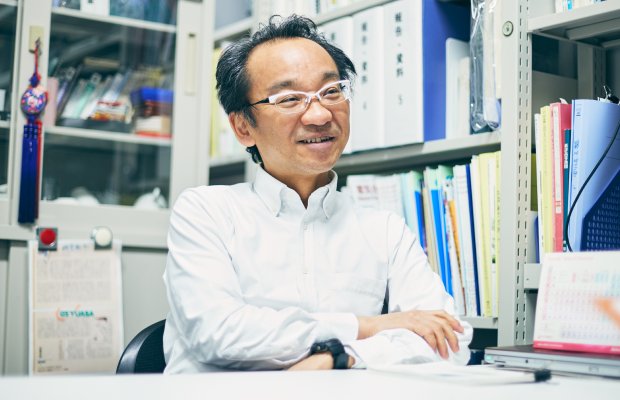科学教育(物理教育、ICT活用、理科教育史、科学リテラシー)

物理の難しさを解明・克服することで、科目本来の楽しさと魅力を伝える
日常的・直感的な概念と物理学的に正しい概念とのギャップを解明
私の研究室では、物理教育という研究分野に取り組んでいます。私自身、もともとは原子核理論を研究していましたが、物理教育という分野の存在を知り、その奥深さに惹かれて転向しました。この研究分野の面白さは、「素朴概念」と呼ばれる私たちの日常的・直感的な概念と、物理学的に正しい概念との間にあるギャップを明らかにしていくところにあります。例えば、ボールを上に投げた時、上昇中には上向きの力が、下降時には下向きの力が働いていると考えてしまう学習者が多いのですが、実際には重力だけが働いています。このような誤解は誰にでも起こり得るものであり、問題を解けることと、本質的に理解していることの間には大きな隔たりがあります。私の研究室では、この隔たりを埋めるための指導法や教材開発、そして学習者がどこでつまずくのかを科学的に明らかにする研究を進めています。特に、数式・グラフ・文章・図など、多様な表現を使って物理概念を伝える「多様表現」に注目し、問題解答時の視線計測などの手法で学習者の思考過程を分析する実験を行っています。

テクノロジーと教育を融合した多様な研究テーマに取り組む
近年はテクノロジーの進歩によって教育の可能性が広がっています。動画解析や教育用センサーを用いた実験は、従来では難しかった物理現象の可視化や分析を可能にし、学習者の理解を深めます。しかし実際の教育現場では機材や環境が十分に整っていない学校も多く、ICT活用はまだ発展途上です。そこで研究室の学生の中には、新しいテクノロジーを活用した教材や方法論の開発を進めたり、純粋な物理に限定せず、情報学や音楽、アートなどと融合させたSTEAM教育の展開にも取り組んでいる人もいます。
2026年には科学コミュニケーション学科が新設されますが、物理はあらゆる科学技術の基盤となるので、その面白さや原理をしっかり理解した上で、物理教育研究で明らかになっている難しさや学びの本質を学生に伝えることが大事だと考えます。それによって将来、教育に携わる人はもちろん、そうでない人でも物理の原理を社会で活用し、伝達できる人材を育成できると思っています。



教育学と理学を結びつける重要な役割を担う科学コミュニケーション学科
以前行われた高校生対象の調査では、物理を「楽しい」と答えた生徒の割合は3割未満にとどまっています。これは才能や努力の問題ではなく、科目固有の難しさにあり、多くの人が同じようにつまずくポイントを抱えているからです。そのつまずきを共有し、乗り越える方法を見つけることができれば、物理はより身近で魅力的な学問になるはずです。
物理教育研究を主導してきた米国の故L.C.McDerottという研究者は、「物理教育の研究は物理学という学問分野にしっかりと根ざしたものであり、学位も教育学ではなく理学で出している」という言い方をしています。私の研究室は日本でも数少ない理学部に属する物理教育の研究室であり、教育学ではなく理学としての物理教育研究を行っている点が特徴です。そして、科学コミュニケーション学科は物理教育で理学の学位を取得できる日本で唯一の学科として、教育学と理学を結びつける重要な役割を担っていきます。ミクロな世界から宇宙の果てまでを解き明かし、ブレイクスルーのきっかけにもなる物理の楽しさをどうやって表現していくか、学生と一緒に考えていきたいです。