
有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―
電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。
138億年前に爆発的膨張によって始めったとされている宇宙。宇宙の謎を解くカギを握るとされている「素粒子」。素粒子物理学を専門としている石塚先生に素粒子の研究とはどのようなものなのか。そしてどのような「創域」的可能性があるのかをお聞きしました。

宇宙は、138億年前、ビッグバンと呼ばれる爆発的膨張によって始まったとされます。しかしその時何が起こり、なぜいまのような宇宙へと至ったのか、詳しいことはわかっていません。その謎を解くカギを握るとされているのが、物質の最小単位である「素粒子」です。石塚教授は、素粒子について研究する「素粒子物理学」を専門とし、世界の多くの研究者とともに、宇宙の起源を解き明かす手がかりを見つけるための研究を続けてきました。多大な時間と労力を費やす研究であり、道のりは平坦ではありません。それでも多くの人が、その研究に魅了されて努力を積み重ね、素粒子、そして宇宙の姿を少しずつ明らかにしてきました。石塚教授もその一人です。素粒子の研究とはどのようなものなのか。そしてどのような「創域」的可能性があるのか――。石塚教授に聞きました。
石塚 正基(いしつか まさき) 1999年 京都大学理学部卒業、2004年 東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会 特別研究員、インディアナ大学研究員、東京工業大学理学院助教、本学理工学部准教授を経て、2020年より同教授(2023年4月より現職の名称へ)。専門は素粒子物理学。
私の専門分野は素粒子物理学で、その名前の通り、素粒子についての研究を行っています。素粒子とは、物質を構成する最小単位の粒子のことで、電子やクォークなどの存在が知られています。その中に「ニュートリノ」という素粒子があるのですが、その性質や挙動について理解することで、宇宙とは何か、物質とは何かといった謎を解く手がかりが得られることがわかってきました。そのため近年、ニュートリノの研究は様々に進んでおり、とりわけ日本のニュートリノ研究は世界をリードし続けてきました。私も長く、ニュートリノの研究に携わってきており、現在も複数のプロジェクトに参画して実験、研究を行っています。
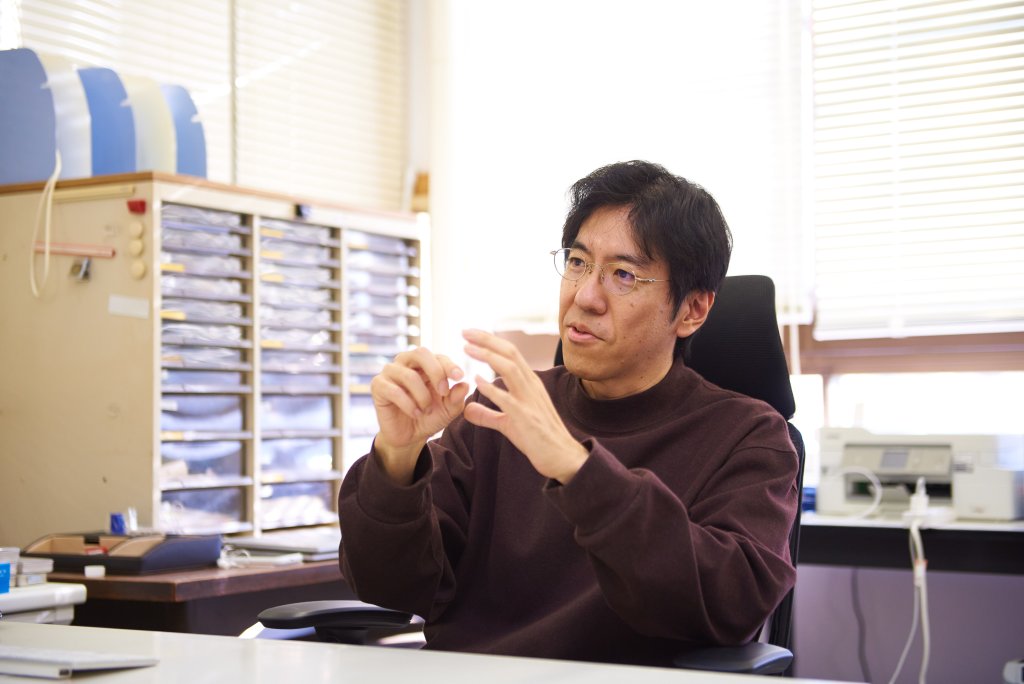
我々人間は古くから、自然界にあるすべてのものは、それ以上細かく分割できない何らかの基本要素からできていると考えてきました。たとえば紀元前には、自然界は土、水、空気、火の4つの「元素」から成り、それらがいろんな配合で集まることですべてのものができているとする「四元素論」が信じられていました。しかし時代が進むにつれて、これは正しくなく、たとえば水滴は、たくさんの水分子が集まったもので、水分子は、さらに酸素原子と水素原子がくっついてできたものである、といったことがわかってきました。そして原子を拡大して見てみると、原子はさらに原子核と電子に分かれ、原子核は陽子と中性子に分かれることがわかり、陽子はさらに小さなクォークという要素からできていることがわかりました。いまのところ、クォークはそれ以上細かく分けることはできそうにないため、これが最小単位、つまり、素粒子の一つであろうと考えられるようになりました。そのように長い時間と様々な理論、実験、観測によって人類は、これが素粒子だろうというものを一つずつ見つけていき、現在は素粒子標準模型というモデルで予言される全ての素粒子の存在が確認されています。素粒子の種類は数え方にもよるのですが、17 種類あるとされています。一方で、暗黒物質(ダークマター)の存在など、素粒子標準模型では説明できない現象も確認されており、今後の研究によって別の種類の新しい素粒子が発見される可能性もあります。
宇宙は、いまから138億年前、ビッグバンと呼ばれる爆発的な膨張によって始まりました。そして現在に至るまで一貫して膨張し続けてきたと考えられています。なぜそんなことがわかるのかと言えば、ビッグバンから間もない時期に発せられた光がいまも宇宙に漂っていて、それを観測することができるからです。しかし、その光によって私たちが直接観測できるのは、ビッグバンが起きてから約38万年後までのことです。最初の38万年間は宇宙が高温であったために原子が形成されておらず、電子や原子核との干渉により光が長い距離を進むことができなかったからです。
そこで、それより前のこと、つまりビッグバンが起きたまさに直後のことを知るためには、素粒子について理解することが重要になってきます。その時期の宇宙では、素粒子が作られては消え、作られては消えるといったことが繰り返されていたと考えられています。そこで素粒子がどのように振舞っていたかがわかれば、ビッグバン直後の宇宙で何が起きどのようにして現在の宇宙が形成されたのかの手がかりがつかめるかもしれないのです。
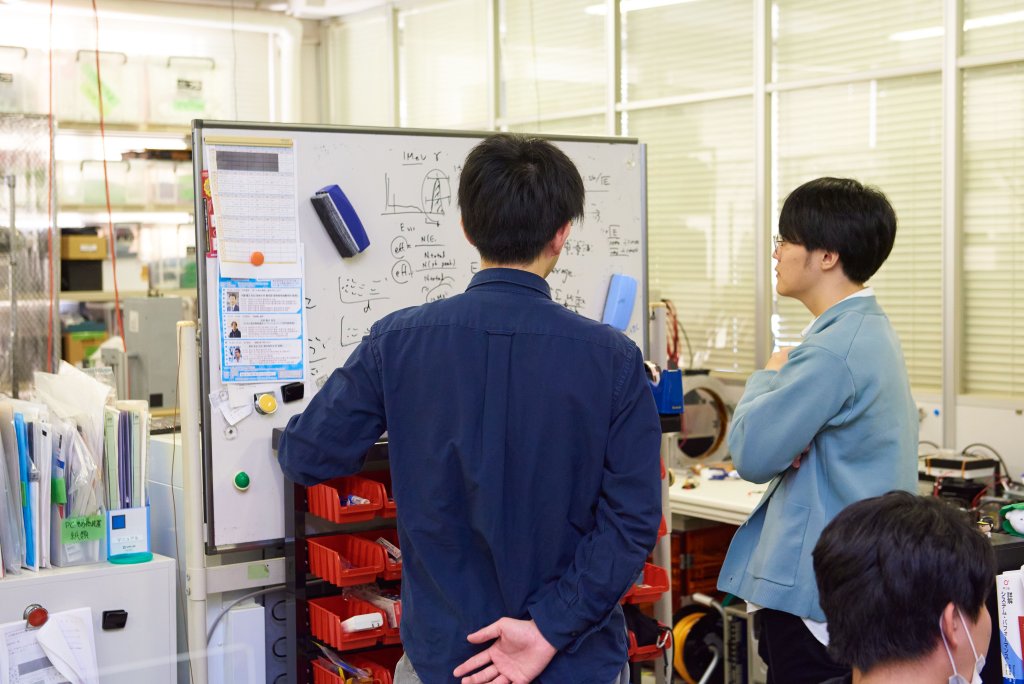
一つには、加速器と呼ばれる巨大な施設を使った実験があります。加速器はその名の通り、電子や陽子などの粒子を加速して、超高速、超高エネルギーの状態にすることができます。そのような粒子同士を衝突させるなどして、何が起こるかを調べます。超高エネルギーの粒子が衝突する時、ビッグバン直後に近い状態が再現されるため、そこで起きていることを調べると、ビッグバン直後のことがわかる可能性があるのです。
またニュートリノの研究においては、巨大な観測装置が大きな役割を果たしています。ニュートリノは宇宙のどこにでもあふれていて、いまこの瞬間も皆さんの体を1秒間に数百兆個が通り抜けているのですが、目で見たり、触って感じたりすることはできず、観測することも困難です。そこで日本では、ニュートリノの観測を主な目的とした実験施設「スーパーカミオカンデ」が岐阜県飛騨市に1996年に建設され、いまも24時間365日、観測が続けられています。この施設は、地下深くに作られた巨大な水槽のようなもので、水が満たされた水槽の壁面には1万本以上の特殊な光センサが取り付けられています。それによって水中で反応したニュートリノの痕跡を捉えるのですが、このような施設を作ってようやく研究に必要な数のニュートリノの観測が可能になります。日本は、ニュートリノ研究で世界をリードしていると言いましたが、この施設の前身の「カミオカンデ」による超新星ニュートリノの観測で小柴昌俊先生が、そして、スーパーカミオカンデによる観測データを使ったニュートリノ振動の発見で梶田隆章先生が、それぞれノーベル物理学賞を受賞しています。
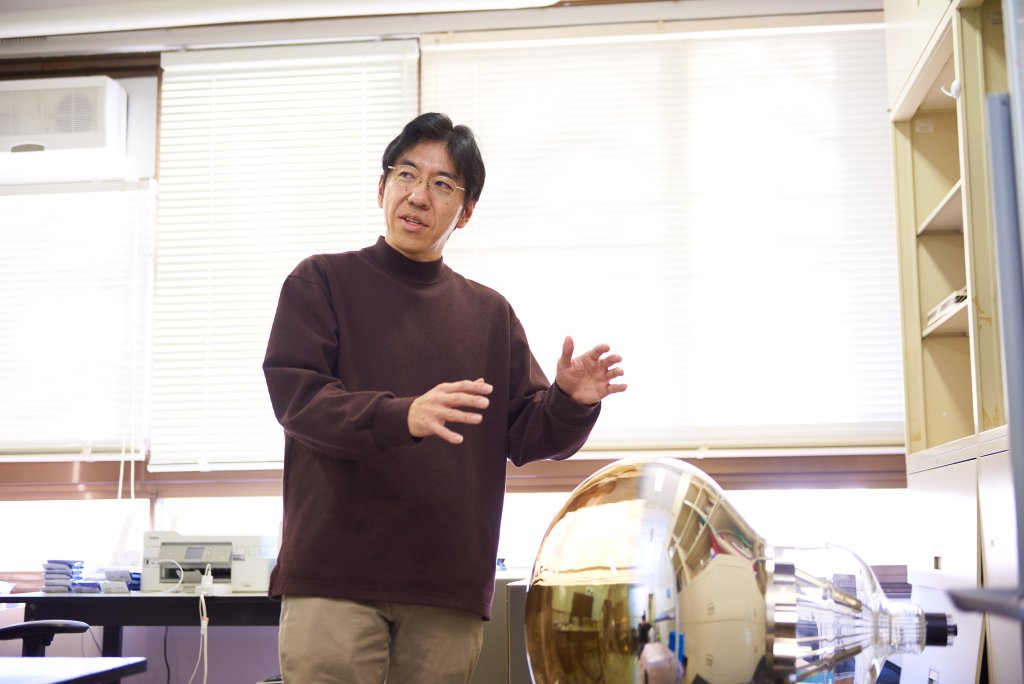
はい、そうです。こうした施設で行われる様々な実験や観測にこれまで参加してきました。大学院では、梶田先生の指導のもと、スーパーカミオカンデを利用したニュートリノの研究を行いました。大学院を修了後はアメリカやフランスで行われたニュートリノの研究に携わっていました。加速器による研究としては、スイスにあるLHCという加速器で「ヒッグス粒子」という素粒子を発見することになったATLAS実験にも参加していました。
現在は、主に2つの実験による研究を行っていて、その一つが、スーパーカミオカンデによる観測です。スーパーカミオカンデでは、太陽、大気中、超新星などから発生するニュートリノの観測の他、素粒子標準模型を超える新しい理論(大統一理論)で予言される陽子が崩壊する現象の探索も行っています。もう一つは、「T2K実験」と呼ばれるプロジェクトです。T2Kとは“Tokai to Kamioka”、つまり、茨城県の東海村にあるJ-PARCセンターの加速器で作ったニュートリノを西に向けて飛ばし、スーパーカミオカンデ(岐阜県飛騨市神岡町の地下にある)で観測するという実験です。これらに加えて、「ハイパーカミオカンデ」という次世代のニュートリノ検出器の建設も進めています。
先ほど、ビッグバン直後の時期に、「素粒子が作られては消え、作られては消える」という状態だったと言いましたが、より詳しく言えば、「何もないところから、“粒子”と“反粒子”というペアが作られ、それがまた消える」ということが繰り返される状態でした。この際、ペアができてまたペアで消えるので、最後はゼロになりそうですが、実際には、反粒子は消え、粒子だけが残りました。それがなぜなのかは解明されていないのですが、それこそが、いま私たちが住んでいる世界です。粒子と反粒子の振る舞いの違いは「CP対称性の破れ」と呼ばれ、粒子だけが残った理由、すなわち宇宙に存在する物質の起源を知るためのカギと考えられています。T2K実験は、まさにそれを確かめることを目的としています。

ニュートリノにはじつは3つの種類があり、空間を飛ぶ間に種類が変わる「ニュートリノ振動」という性質を持っています。たとえば「ミューニュートリノ」というニュートリノをJ-PARCから飛ばすと、スーパーカミオカンデでは「電子ニュートリノ」が観測されたりします。ではそれが、ニュートリノのペアにあたる反ニュートリノではどうなるか。それを知るために、反ニュートリノに関しても同じ実験を行って、ニュートリノ振動を測定します(ニュートリノと反ニュートリノは、J-PARCの加速器で作ることができます)。もしニュートリノと反ニュートリノで振動の確率が異なれば、「CP対称性の破れ」が存在することが実際に確かめられたことになるのです。
兆候は出てきているのですが、まだ、はっきりと「CP対称性の破れ」を確認したと言える段階ではありません。いま、スーパーカミオカンデの後継にあたる「ハイパーカミオカンデ」の建設が進んでいて、2027年の完成予定となっています。さらにJ-PARC加速器の増強も進められており、ハイパーカミオカンデの研究では、よりはっきりとした結果が出るだろうと考えています。

私たちの研究している素粒子、特にニュートリノは、現時点で他の分野に応用するのは難しいと考えています。一方、素粒子の研究の過程で開発された実験技術は工業や医療などへ応用されていますし、加速器で作られる放射光は生命科学や物質科学などの研究に広く用いられています。創域理工学部では様々な分野の研究が行われており、学科間の交流から、私たちも予想していなかった実験技術や検出器の応用の新しいアイデアが出る可能性があります。素粒子の研究分野でも、新しい観測技術から未知の粒子や未知の現象が発見される例が多くみられます。この試みは現在も続いており、例えば、暗黒物質の探索では、環境放射線によるノイズを減らすため、非常に純度の高い物質で検出器を製作するための工夫を模索しています。また、私たちの研究室では機械学習をデータ解析に応用することにより、信号とノイズを区別するような研究も行っています。情報や工学を専門とする方たちと連携することは私たちにとって大きな意味を持ってくると思います。

創域理工学部へと名称が変わる直前の2022年に開かれた「創域特別講演会」において、機械航空宇宙工学科の小笠原宏先生とともに「宇宙を取り巻く融合研究」というテーマでお話をしたことがあります。宇宙の研究について、私が理学系の話をして、小笠原先生が工学系の話をするという場でしたが、その際、様々な専攻の学生が聴講し、質問もいろいろ出て、私自身にとってもすごく刺激的な機会でした。その時に、同じ野田キャンパスで、異なる分野の学生や教員がとも学び、研究することの意味を感じました。特に、理学系と工学系では、進路への意識が異なる場合も多いでしょう。学生たちにとって、異なる分野の人同士が積極的につながりやすい環境で学べることは、自身の将来を考える上でもとても有用なはずです。
また私は、高い専門性があってこそいい「創域」が生まれると考えています。ただ単に異なる分野の人と繋がるというだけでなく、よい繋がりを生むためにも、それぞれが高い専門性を身に付けるために一生懸命取り組んでほしい。それは教員同士も同じです。創域理工学部が、融合の場であるとともに、そのような意味で、互いを高め合える場になっていったらと思っています。

学生は概ねみな、先に説明したようなプロジェクトでの研究を進めています。ただし学部、修士課程、博士課程で、研究の仕方は違ってきます。まず学部生の場合、スーパーカミオカンデ実験やT2K実験に直接参加することはできないので、現在取り組んでいる実験の改良や別の課題に挑む新しい実験のアイデアをコンピュータの中で仮想的に構築してシミュレーションしたり、そのような実験で使用する装置の開発・性能評価試験を行ったり、といった研究が多くなります。修士課程や博士課程の大学院生は、スーパーカミオカンデ実験、T2K実験、ハイパーカミオカンデ実験などに参加して研究を行っています。大規模な実験装置を安定して稼働させ、その観測データから新しい研究成果を挙げるために必要な課題は多岐に渡ります。例として、スーパーカミオカンデでは水槽に満たされた超純水の水質や1万本以上の光センサーの特性を理解しないと正確な測定はできませんし、T2K実験ではニュートリノビームの方向や強度などを常時モニターする必要があります。プロジェクトに参加する研究者は、協力してこれらの課題に取り組みつつ、その観測データの解析から素粒子の未知の性質を探る研究を行っています。これは大学院生も同様です。特に、博士課程では研究成果を挙げて論文を執筆することが求められるため、データ解析が中心になります。
いずれにしても、現代の素粒子物理学の実験は、規模が大きく、数百名以上の研究者による国際共同研究が中心となっています。そう聞くと一人ひとりの役割が小さく感じられるかもしれませんが、逆に、素粒子の謎に挑む研究はそれだけの人が力を合わせなければできないプロジェクトだということでもあります。人数の大小によらず、宇宙の謎に挑む研究に携わることは本当に面白く、やりがいを感じています。
現在、岐阜県飛騨市では、ハイパーカミオカンデ検出器を設置するために直径69m、高さ94mの大規模な地下空洞の掘削が行われています。ハイパーカミオカンデ実験では、先のニュートリノのCP対称性の破れの研究以外にも、超新星からのニュートリノの観測など、様々研究成果が期待されています。中でも、「陽子崩壊」と呼ばれる現象の探索は世界中の研究者が注目する重要な研究テーマです。素粒子の間には4つの力が働くことが知られていますが、それらを統一する新しい枠組みを与える理論として有力視されているのが「大統一理論」です。大統一理論では陽子が崩壊する現象が予言されます。大統一理論は、特にビックバン直後の超高エネルギー状態の宇宙で重要な役割を果たしていたと考えられています。陽子の崩壊は未だ確認されていませんが、もしハイパーカミオカンデで観測されれば、大統一理論が正しいことが実証され、素粒子と宇宙の理解が大きく進むことになります。陽子崩壊の発見は研究者としてのライフワークのような位置付けであり、ぜひ実現したいと考えています。
いま、さまざまな場面で、効率を重視する考え方が広がっていますが、それでいいのだろうかと、最近よく感じます。学問を学ぶ場合も、いろんな参考書を斜め読みして、簡単に答えを導けるコツを身に付けるのが効率的かというと、私はそうは思いません。基礎となる教科書をしっかり理解していくのが、結局は一番の近道なのです。
地道に見えても、目の前のことに一生懸命に取り組み、一つ一つを自身で体験しながら学んでいくことが大切です。そして専門性を確立する。その上で視野を広げ、創域的な意識を持っていくことで、きっとその先にいろんな可能性が見えてきます。私たちの研究に興味を持ってくれた人は、是非扉をたたいてもらえたらと思います。
