
有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―
電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

音や映像に対して人が何を感じ、身体がどう反応するのか。建築音響を専門としてきた朝倉准教授は、現在、音に対する人間の心理的・生理的反応を中心に研究を進めています。環境音や騒音など、幅広い音を研究対象としています。
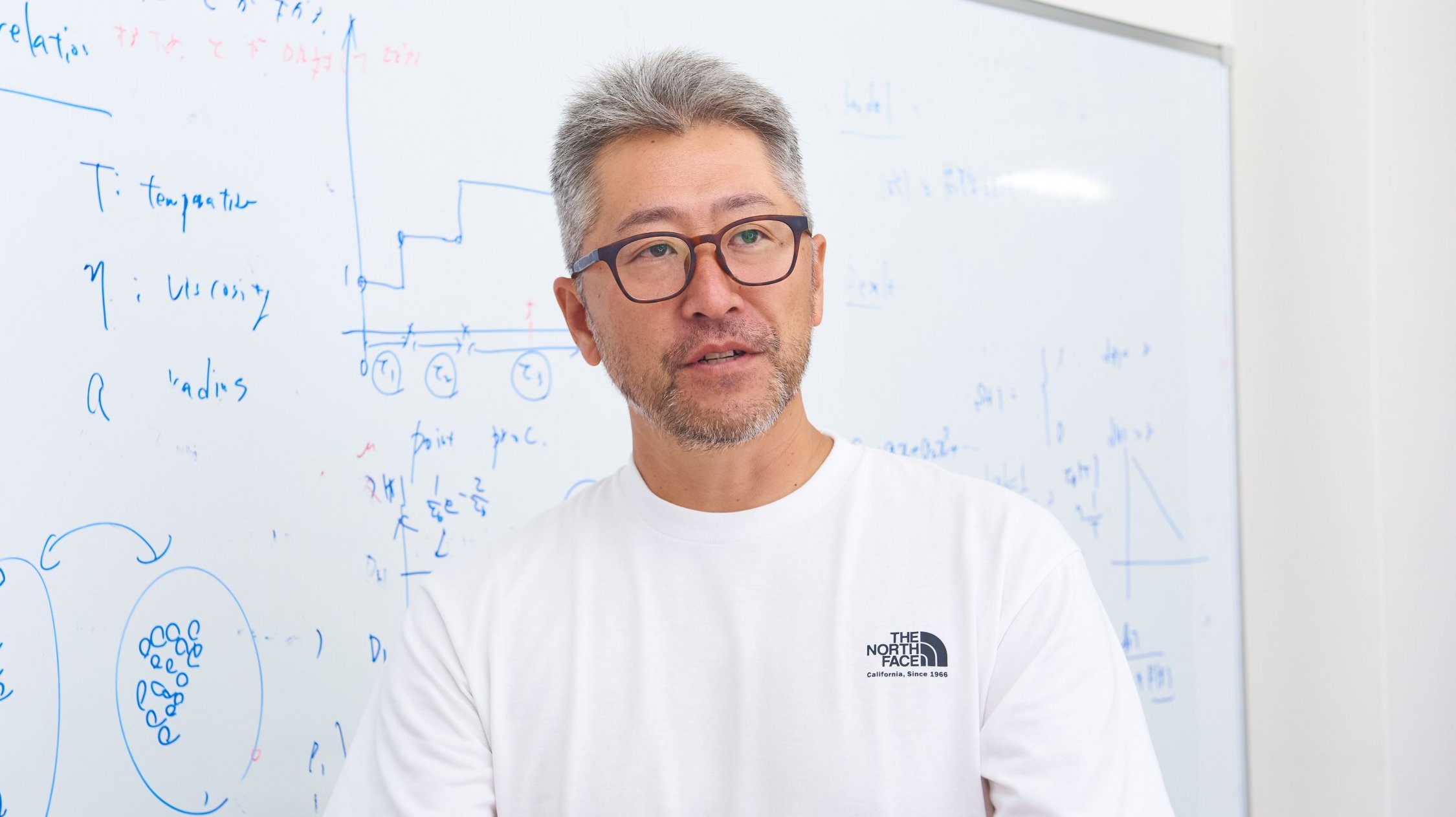
秋元琢磨教授は、多数の粒子のふるまいを確率や統計を使って解明する統計物理学の中でも、未解決の課題に挑んでいます。 物理現象を超えて広がるこの学問の可能性と、「研究教育」への熱意を語ります。

都市計画を専門とする伊藤香織教授は、都市に関する多様な研究と実践を行っています。空間情報の分析をはじめ、「シビックプライド」や公共空間の活用を促す「ピクニック」など、都市の魅力を高める研究をしています。

電気化学は、化学反応と電気の相互変換による現象を扱う分野です。橋本永手講師はこの手法を活かし、海中の杭抜きや土の脱水など、インフラ構造物の建設・保全技術の開発に挑戦。全研究を共同で進め、異分野連携にも積極的に取り組んでいます。

後藤允准教授は、金融工学の「リアルオプション」や企業分析手法「プロセスマイニング」をサッカーへ応用する研究を進めています。選手の市場価値算定や戦術分析に活用し、金融・ビジネスの枠を超えた創造的研究を展開しています。
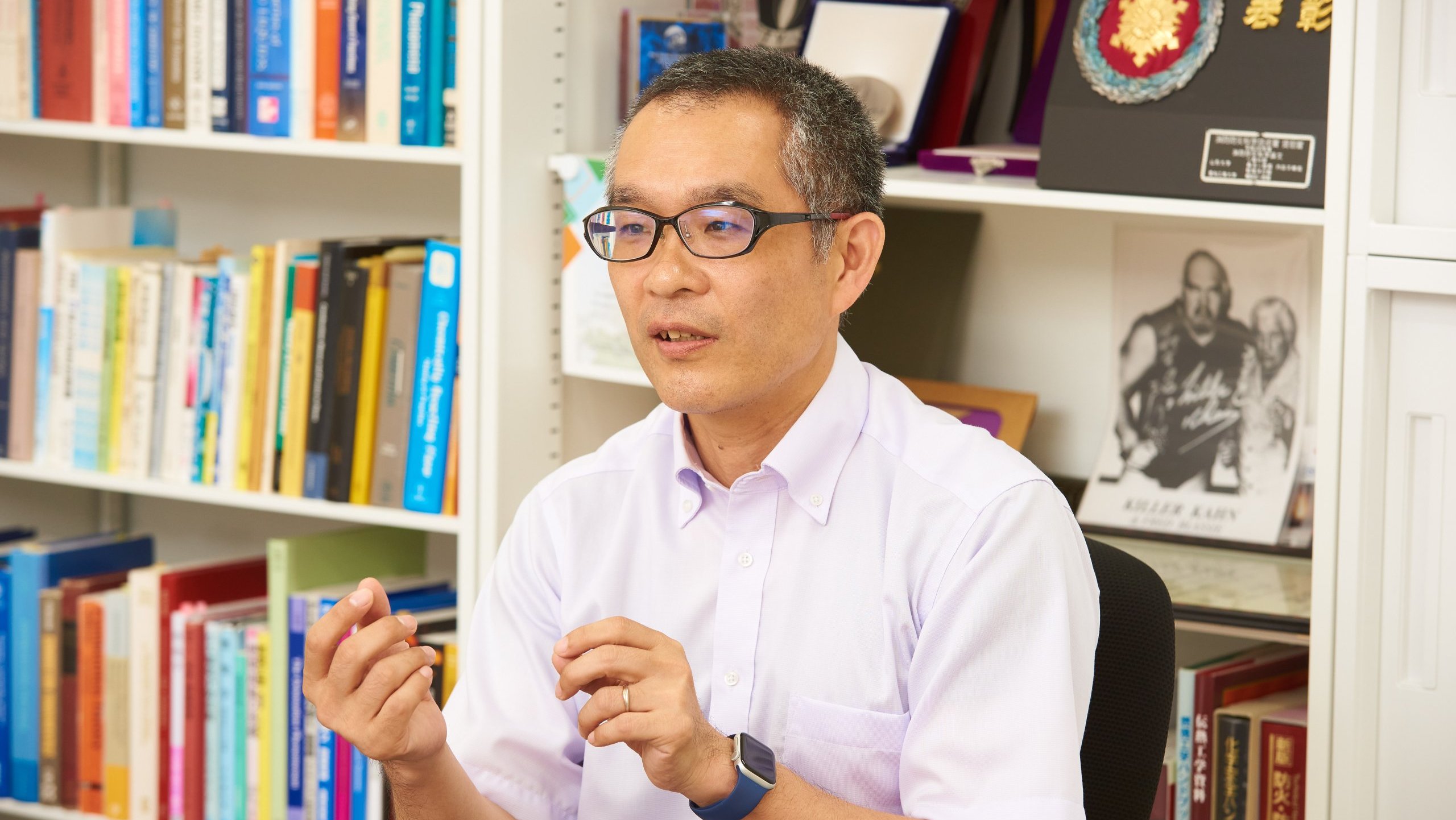
桑名教授は、火災・爆発、最近多数発生している大規模な山林火災などの「火災」に関するメカニズムの解明を目指して研究を進めています。

バイオマスをガス化し水素を生成・貯蔵・利用する研究を20年以上続けてきた堂脇清志教授。下水汚泥を原料にしたこの取り組みは、多分野の連携により社会実装が現実に近づいています。